こんにちは、タカヒロです。
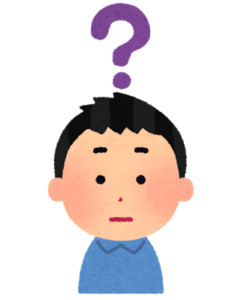
そうした疑問にお応えしていきます!
この記事では「ストーリーリテリング」のやり方とメリットをご紹介します。
ストーリーリテリングとは「キーワードや絵を参考にして、学習した英文を自分なりに再生する活動」です。
なかなかハードルが高いように聞こえますが、ステップを踏んでいけば、それほど難しくはありません。
この記事の内容
ストーリーリテリングのやり方とメリット
筆者の経歴
・公立中学 教諭5年
・イギリス大学院でMA TESOL
・県立高校 教諭2年
・私立大学、高校 非常勤講師

授業作りの参考になれば幸いです!それではどうぞ。
【中学英語】ストーリーリテリングのやり方と授業の流れ
まず、僕が中学校2年生を対象に行っていた授業の流れをご紹介します。
ストーリーリテリングを取り入れた授業の流れは以下の通りです。
1 新出単語を確認する(3分)
2 学習する本文を導入する(5分)
3 音読指導を充実させる(10分)
4 内容理解やQ&Aを行う(5~10分)
5 ペアで穴埋めプリントを用いて活動させる(10分)
6 先生の所へ来て、指定された写真を再生する(10分)
・進出単語の意味を調べてくる
・本文を読解し重要箇所(教師側に指定する)を訳してくる
ということを予習としてノートにやらせてきます。
取り扱う文法に関しては前時に導入済みの状態になります。
詳しく見ていきましょう。
1 新出単語を確認する(3分)
自分で読めない単語、意味の分からない単語があっては活動がスムーズにできません。
まずは教員主導でコンパクトに新出単語を確認します。
2 学習する本文を導入する(5分)
僕の場合は、付属のピクチャーカードを元に、紙芝居をしながら本文を導入します。
一周目は普通に教員が通して読みます。
二周目は教員が文の途中で止め、その続きを生徒に言わせます。
三周目は教員が出だしのみを読み、その続きを生徒に言わせます。
※二周目、三周目では教員はピクチャーカードの該当箇所を指差しながら、口パクをして補助します。
そのように導入すると、教科書全体の内容を大まかに英語だけで導入できます。
その後、英語で2つ、3つ簡単な内容理解の質問をします。
ここまでは英語オンリーで行います。
3 音読指導を充実させる(10分)
続いて教科書を開かせて、どんな英文だったのかを目で確認させていきます。
CDを一回通して流し、その後教員の後にリピートさせて本文を音読していきます。
僕の場合は、次にペアで交互読みを2周、終わったら個人で3分間音読タイムを設けて、ひたすら音読をさせます。
教員は机間指導をして、英語が苦手な生徒の補助に入ります。
生徒同士でも分からないところは聞き合うという雰囲気を作っておくと、教員側も楽です。
4 内容理解やQ&Aを行う(5~10分)
僕の場合はパワーポイントを使いながら、重要表現、重要文法事項の確認をします。
ここは日本語の方が効率が良いし、生徒も理解しやすいので日本語です。
ポイントは重要な文はしっかり解説しつつ、全体的には手短にササっと行うことです。
10分以内がベストです。
5 ペアで穴埋めプリントを用いて活動させる(10分)
穴埋めプリントを配布し、ペアでリテリングの練習をします。

写真①

写真②
プリントの表には写真①を裏には写真②を印刷しておきます。
一人が奇数番号の文、もう一人が偶数番号の文と、交互に読み合っていきます。
自分たちのペースで何度も何度も読ませます。
左側の絵に指を差させて、どこを読んでいるのか理解しながら読むよう指導します。
だいたい読めるようになってきたら、いよいよ裏面のキーワードのみのプリントを使って本文を再生していきます。
プリントの表に戻ったり、教科書に戻ったりしながら何度も何度も読ませます。
6 先生の所へ来て、指定された写真を再生する(10分)
そこまで出来てきたら、いよいよ教員のところへペアでやってきて、発表をします。
黒板には導入で使ったピクチャーカードを貼っておいて、教員が一つの絵を指定します。
生徒は指定された絵に関して、黒板のピクチャーカードを指さしながらペアでリテリングしていきます。
チェックするのポイントは、
・主語+動詞といった文の骨格がしっかり組み立てられていること
・進出単語を含め、理解可能な範囲で英語らしい発音で読めていること
です。
学習した文と全く同じに再生する必要ありません。
要は「絵の内容を、自分なりに英語で説明できている」となればタスク完了です。
教員から合格を貰ったペアは、英語が苦手は生徒たちのスモールティーチャーになります。
本当は写真を指定せずに全部再生させたいですが、時間の関係上出来ていません、、、。
しかしどこを指定されるから分からないので、生徒は全部を練習して出来る状態になっている必要があります。
中学英語の授業でストーリーリテリングを行うメリット
ストーリーリテリングを行うメリットは以下の通りです。
・アウトプットすることを念頭に置いてインプットすることができる
・クラスが活発になる
・合格すると達成感を味わえて、モチベーション維持に繋がる
順番に見ていきましょう。
アウトプットすることを念頭に置いてインプットすることができる
生徒がどういう時に効果的に単語や熟語をインプットするのかというと、
「その単語や熟語の意味を知らないと、今目の前にある情報を読み取れないとき」
です。
ストーリーリテリングでアウトプットすることが事前に分かっていれば、進出単語を確認したり本文を導入する時点から、生徒のインプットの質が高まります。
英語が得意な生徒は導入時点で3回読んでだいたいストーリーリテリングできてしまうほど、集中してインプットします。
クラスが活発になる
ストーリーリテリングの授業では後半の20分はずっとペアでの活動です。
先生が長時間説明しても、生徒の実質的な英語力は伸びていきません。
トレーニングの時間をどれだけ確保できるかが勝負だと思います。
授業の後半20分はずっとわちゃわちゃしながら、それぞれ自分たちのペースで活動します。
何回かやっていくうちに生徒も慣れて要領を掴んできます。
慣れてくると益々アクティブに活動するようになります。
合格すると達成感を味わえて、モチベーション維持に繋がる
生徒にとっては、日常ではなかなか英語を使う機会がないため、授業の中で「英語を使って何かを行い達成感を味わう」ということは非常に重要だと思います。
スモールステップで「できた」という体験を積み重ねていくことが英語学習のモチベーション維持に繋がります。
英語で何かをやって認められたら嬉しいですしね。
また、多くの生徒は「受験勉強も大切だけれども、英語を話せるようになりたい」という願望を持っています。
ガンガン言葉を発して、自分で言える表現を増やしていくということは、生徒の要望ともマッチしているところが多いです。
ストーリーリテリングを授業に取り入れよう!
今回の記事では、ストーリーリテリングをやり方とメリットについてご紹介しました。
ストーリーリテリングの活動は生徒と先生共に慣れてくればいい所尽くしの活動だと思います。
是非新学期に取り入れてみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。こちらの記事も是非合わせてご覧ください。

