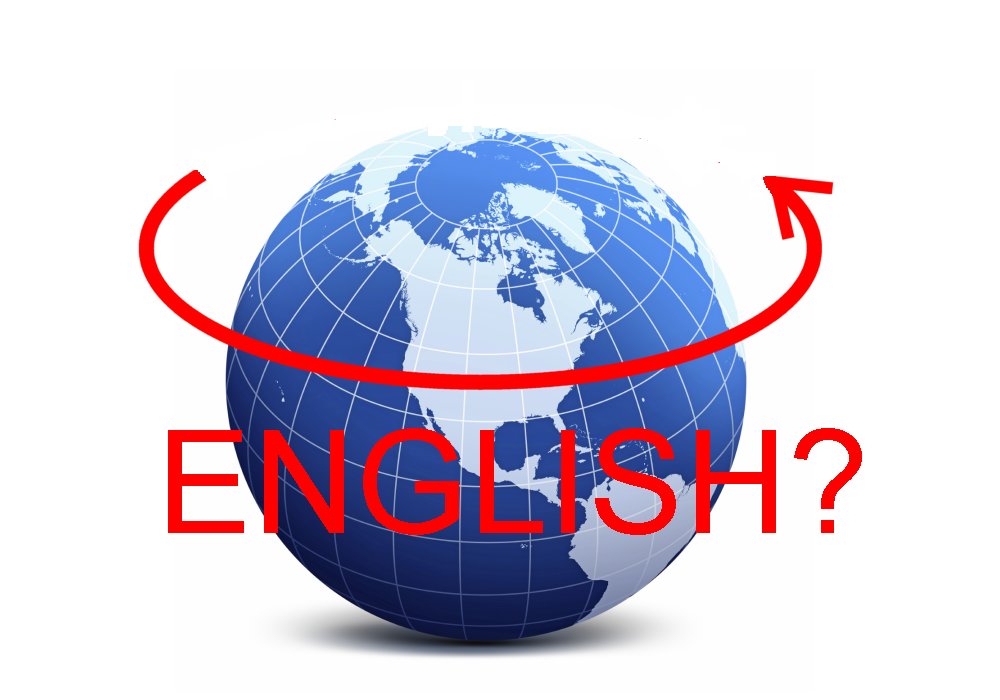こんにちは、タカヒロです。
最近英語学習の中で耳にするようになってきた「リンガ・フランカ」。
「英語はリンガ・フランカとして重要な役割を担っている」
といったように使ったりしますが、どのような意味なのでしょうか?
この記事では「リンガ・フランカ」とは何なのかを解説していきます。
リンガ・フランカとは?
リンガ・フランカとは、世界のどの地域ということに関わりなく、言語の通じない人々同士が通商などのために用いる「共通語」「公用語」です。
例えば、日本人と中国人、タイ人など、英語を母国語としない国の人々とやり取りをする際に英語が用いられる場合、英語はリンガ・フランカとして使われています。
リンガ・フランカは現代の英語だけではありません。
歴史を遡ると、第二次世界大戦後の共産圏内ではロシア語がリンガ・フランカであり、
さらに遡ると、ルネサンス期のヨーロッパでは学問の象徴としてラテン語が普及していました。
学者たちがギリシア語の古典をラテン語訳したため、ラテン語ができればギリシアローマの古典を一通り読めたと言われています。
リンガ・フランカとしての言語
ここからは、リンガ・フランカについて疑問に思うことをまとめていきます。
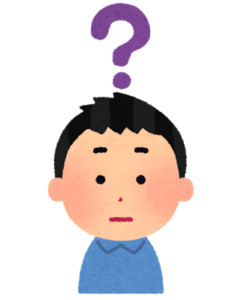
そうした疑問が思い浮かびます。
しかし中々そうはいかないのですね。
言語は文化と密接に関わっているからです。
その地域の文化があるから言語が生まれ、言語があるから文化が育ってきたわけなのですね。
もし日本語が全く使われなくなってしまったら、日本の文化は崩壊してしまいます。
「いただきます」「お疲れ様です」なんて言えなくなるし、長らく歴史の中で培ってきた日本独自のものを語り継げなくなります。
そうすると、日本人って何者なんだ!?とアイデンティティさえ疑うことに繋がりそうです。
また、現在英語が世界中で使われているのは18世紀のイギリス、19世紀のアメリカによる影響が大きいです。
世界での「権力」を栄養として伸び広がっていったわけです。
歴史を振り返っても、共産圏はロシアの支配下に、ラテン語が普及した中世ヨーロッパも、ローマ帝国の支配下にありました。
現在、英語を使うということは英語圏の文化に知らぬ間に浸っているということです。
もし英語だけを使うとなってしまったら、世界中の様々な文化が英語圏の文化に浸食されるということになってしまいます。
言語と文化は繋がっているため、リンガフランカだけの世界にはならない。
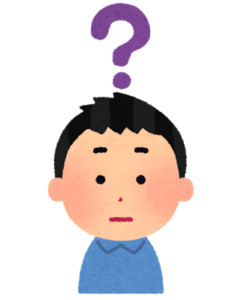
実際その動きもありました!
「平等な新しい言語を作ろう!」ってことで、ヴィラピュック語やエスペラントという言語が作られたりしました。
しかしうまく広がらなかったのですね。
言語は文化の中で常に新しく生まれ変わっていくからです。
日本語でも「ウザい」「キモい」「タピる」、、、どんどん新しい言葉が生まれていきます。
言語が生きたものであるためには、時代に合わせて新しい単語や表現を次々に生み出していく必要があります。
人口言語ではそれができません。いちいち世界中の代表を集めてこの単語をこういう意味で使おう、なんて確認やってられないですからね。
そういったわけで、人口言語は普及していきませんでした。
言語の生まれ変わりに人口言語はついていけない。
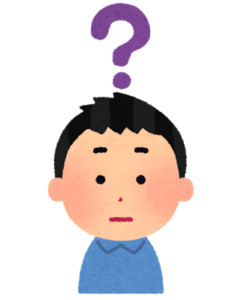
実際これだけ英語が世界中で使われていて、「リンガ・フランカ」と呼ばれるまでになっているわけですから、そのメリットを利用しましょう!

上の図のように、
英語はイギリスやアメリカなど第一言語として英語を使う国から、インド、シンガポールなど第二言語として英語を使う国、さらに日本、タイなど外国語として英語を学ぶ国々とどんどん広がっていきました。
英語が出来れば文化に関係なく世界中の英語が出来る人とやり取りができるなんてほんと素敵なことです!
ただし、英語は英語圏の文化が背景にあるということを念頭に置いて、
・文化的に侵略されないように気を付けること
・英語をコミュニケーションツールとして使うこと
が重要になります。
まとめ
この記事では「リンガフランカ」についてご紹介しました。
英語を学ぶことが重要視されていますが、英語には英語圏の文化が表裏一体になっていることを意識して、日本人としての感覚を大切にしながら学び続けていきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
こちらの記事でも第二言語として英語を学ぶことに関する情報をご紹介しています。
是非合わせてご覧ください。
-

-
【言語学の革新者】チョムスキーの生成文法を分かりやすく解説!
続きを見る
-

-
【英語教師は知っておきたい】第二言語習得論の重要用語10を解説
続きを見る
-

-
【第二言語習得論】が良く分かるおすすめ本5冊+番外編3冊
続きを見る
ではまた!